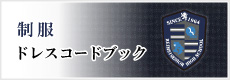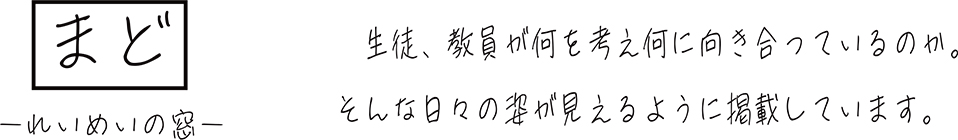2021年8月20日
尾植 香織

「保護者対象動機づけ面接勉強会」。仕事や家事をひと段落終え、週に1回、平日夜7時から集う。
まずは、前回の宿題の確認から。
「息子がゴミ出しを担当してるんですけど、それしか任せてないのに、ただそれだけのことをなかなかしてくれず、それを指摘すると“今やろうと思ってたのに、言われたからやりたくなくなった。もうやらない!”それに対して“じゃあ、もうお母さんもごはん作らない!”と返すと“じゃあ作らなくてもいいよ!”とこんなやり取りの繰り返しで、困り果てていたのですが、今回の宿題が出されたことで、職場の同僚に声を掛けるように、相手の状況に気を配りながら“今ちょっといい?お母さん今ちょっと手が離せなくてごみを出し てきてくれたら助かるんだけど、いいかな?”といった感じでお願いしたら、今までのやり取りが嘘のようにすんなりと機嫌よくゴミ出しに行ってくれたんです。ビックリしました!これからは、息子と思わずに仕事仲間だと思って接することにします(笑)」
「実際あまり意識できてなかったです・・・ただ、一緒に料理をする機会があったのですが、味付けについては言いたい気持ちをぐっと堪えて任せることにしました。もし、こちらがあれこれと指示を出していたら、塩コショウの分量までも細かく聞いてきたでしょうね。子どもが試行錯誤するチャンスを奪うことになっていたかもしれませんね。」
「“今ちょっといい?”というフレーズを一言入れるだけで、子どもの聞く姿勢が変わるということを実感しました。一方的にこちらが言いたいことを言っている時はスルーされることが多かったけど、その一言があるだけで、子どもからも一言二言返ってきてやり取りが生まれ、こちらの話をしっかり聞いてくれていると感じられました。」
5回シリーズのこの勉強会では、1時間で学んだ勉強を実際に1週間実践してみるという宿題が出される。
頭では理解できても、実際やってみるとなかなか難しい。上記は「アドバイスをする時は、許可を得てから」という宿題の感想。
大事にしているのは、この保護者同士の振り返りの時間。机上の学びよりも、今まさに子育てに向き合っている戦友達の生の声のこそが心に響く。他者の発言が自分を写す鏡となり、自律性を尊重されつつ、強制されずに自分の理想とする子育てへと動機づけられていく。「自分だけじゃないんだ」とノーマライズされることにより気持ちが軽くなったり、他者との交流で見方が広がり、それぞれに感じ、考え、変化のきっかけが生まれる学びの場となる。
5回それぞれにテーマを設定している。例えば、「共感」がテーマの日なら、こんな感じで進む。
「うるさい!お母さんには関係ないでしょ!」と言われたらどう返しますか?
子どもが発したその言葉の裏側を想像してみましょう。
「関係ないと思うんだね」
「そっとしておいてほしいんだね」
「今は話したい気分じゃないんだね」
「自分で考えたいんだね」
様々なアイデアが出された。どれも魅力的だ。
どれが正解か?それは実際にその言葉を伝えてみなければ分からない。その言葉を返した後の会話がどのようになっていったか。それまでの関係性や文脈によって同じ言葉を発したとしても結果は異なって当然だ。
たとえその言葉が正解でなかったとしても、自分の考えや価値観を一旦棚上げした上で、相手の目を通して世界を見ようとする姿勢さえあれば道は開けてくる。
とはいえ、実際に「うるさい!」なんて言われたら咄嗟にそんな言葉出てこない・・・ということで、カードの表に普段の会話の中で「言われて困る一言」を書き、その裏に「共感的な返し方」を書いて、いざという時のための「切り札」を用意する。
それまでは、その一言がきっかけで言い争いが始まる嫌なフレーズだったのが、この返し方でいつもの会話にどんな変化があるのか試してみたいと思えると、ある意味言ってほしいフレーズに変わる。
また、「是認」がテーマの日には是認のエクササイズをしてみる。
二人組になって、話し手と聞き手に分かれる。話し手は自分の欠点や上手くいっていない出来ごとについて5分間話す。聞き手は話し手が話し終えた段階で、その方のネガティブな話を聞きながら感じたその方の強みを相手に伝えるという演習。
「こんなに集中して他人の話を聞いたことはなかったかも。子供の話も適当に聞き流しているなぁと改めて感じた。」
「その人の良いところを探そうと必死だった。」
「最近、褒められたことがなかったので、単純に嬉しかった。」
「主体的・対話的で深い学び」。これは決して子どもだけじゃなく、大人にとっても大切なもの。正解を教えられても、行動に移すかどうかは本人次第。気づきや体験を通しての学びが変化を促す。
大人が正解を知っているから、子どもにはそれを教えなければという責任感から、子どもの主体性を奪い大人の価値観を押しつけていては、子どもが「対話」を大切にしながら「深く学び」未来を創造していくことは望めない。
このことをこの勉強会で体感してもらえたらなぁとの期待を込めている。
私も2男1女の親である。
保護者の方々との「主体的・対話的」な学びの時間をじっくりと味わいながら、子ども達の変化を信じられる大人ありたいと思う。
【この記事を書いたひと】
尾植 香織 (教頭/数学科)
好きな炭水化物:塩むすび(炊き立て)
好きな食べ物:餃子、パフェ
趣味:ランニング、草むしり、読書
一日10キロは走らないと気が済まない
ランニングの化身。座右の銘は「足るを知る」、
座右の書は「子どもへのまなざし」(佐々木正美)