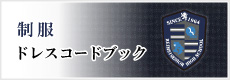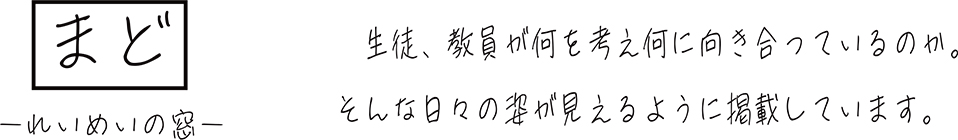2021年8月24日
副田 拓志
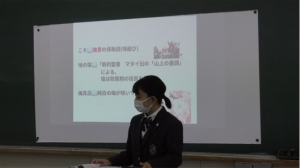
詩の単元と短歌・俳句の単元を生徒に授業してもらおう。
このようなことを考えたのは、そういう他校の実践記録を幾度か読んでおり、興味があったのに加え、より深い学びに向かう生徒を育てたいという心中密かな願いへの方法論の一つとして検証したいと考えたからである。
とはいえ、最初から生徒に授業をやってもらうのもハードルが高いので、まずは私が近代詩の概論的な授業を行った。その後、教師用の資料の使い方や、進行の仕方など、授業方法のレクチャーを挟んで、三,四人を一チームとして、各チームでの準備期間を与え、実際に授業をしてもらった。授業が始まるまでは本当に大丈夫かな、と私の方がひやひやしていたが、生徒たちは思ったよりも緊張しておらず、また授業を受ける生徒もいつもよりのびのびとしていた。(なんか悔しい。)
生徒たちはiPadを一人一台持っているのでITスキルを駆使して立派な資料を作り上げてきたり、また、あえて板書で挑むチームもあったりと、それぞれの個性が反映されていた。それぞれの授業内容については、あらためて語っても冗長になるだけなので省くが、写真を見るだけでも、生徒たちがいかに学び、いかに伝えたかがわかっていただけるであろう。
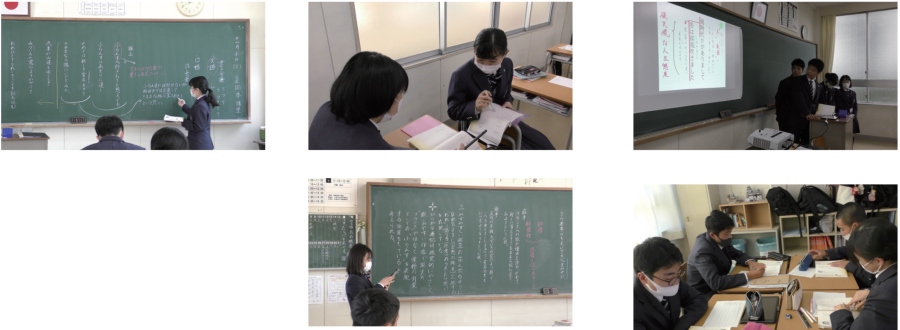
「どのようにして学ぶのか」
さて、普段、授業をしていても我が学校の生徒たちは非常によく集中して授業を受けている。それは昔ながらの教師が一方的に話し、板書をするだけの授業でもそうである。
しかしながら、今回の生徒が自分たちで授業をするという実践において浮き彫りになったのは、前に立つのは教師でなくてもよい、ということに他ならない。今回、私が行ったことは、生徒に専門的な資料を与え、それを伝達させる役割を与える、というなんともおおざっぱな仕掛けを作っただけである。
それでも、生徒は普段通り、あるいは普段以上に学んだのではないだろうか。彼らの行った授業や作成された資料を見れば、それは明らかである。
一つ留保があるとするならば、今回のようなことを毎回行うのは、生徒の負担を考えると、現実的に無理がある。(彼らには現代文以外にも多くの学ぶべきことや、熱中すべきことがある!)やはり、多くの場合で教師が授業の進行役、伝達役となるのもやむを得ない。ただし、形態を変えて教師が前に立つとしても、生徒の学びがより今回のような状態に近くなる授業は不可能ではないと考えている。というよりも、それを追求していくことが、教師がすべきことだといえる。そのような考えにあらためて行き着き、なんともこれは気を引き締めていかねばなあ、と考えている次第である。
【この記事を書いたひと】
副田 拓志 (文理科 2 年担任 / 国語科)
好きなラーメン:二郎系
好きな哲学者:ニーチェ
趣味:お取り寄せグルメ
主に現代文を担当している。軽妙なトークと
多彩で論理的な指導で生徒からの信頼も厚い。
関東出身なので鹿児島のラーメン屋で漬物が
出てきたことがカルチャーショックだった。